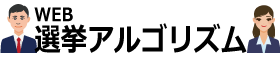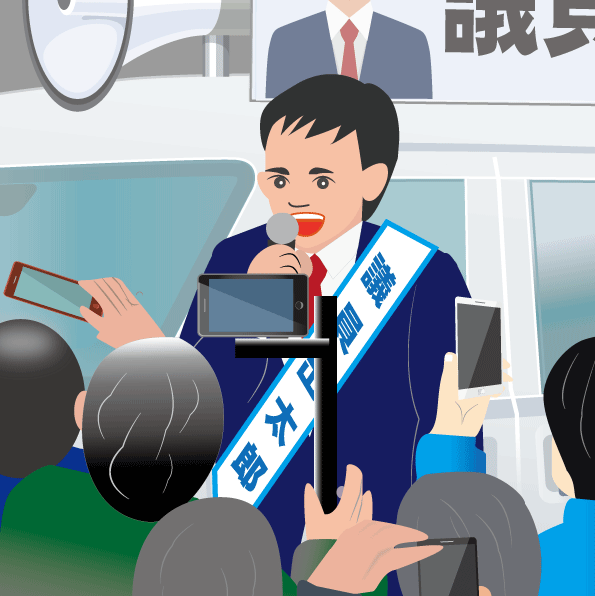法整備の現状と必要性
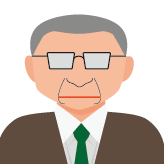
出太郎君の言うように、これらの事例に共通するのは、SNS運用という専門性の高い業務を外部の専門業者(PR会社、コンサルタント、制作会社など)に委託し、その対価を支払うという行為が、公職選挙法の「選挙運動ボランティアの原則」および「買収罪」の規定とどのように整合するのかという問題です。
ここでまず法整備の現状を見てみましょう
公職選挙法上、「選挙運動」とは「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」と広く解釈されています。業者が候補者の当選目的を認識し、主体的・裁量的にSNSコンテンツの企画、制作、配信、分析、戦略立案などを行えば、それは紛れもなく「選挙運動」に該当し得る。これに対して対価を支払うことは、原則として買収罪となりえます。
従来、選挙コンサルタント等は、「告示前の活動(選挙準備活動)は有償、告示後の選挙運動期間中の活動はボランティア」という建前で、法の規制を回避しようとする動きもありました。しかし、選挙全体が一体の活動である以上、告示前後の活動を切り離して対価性を判断することは実態にそぐわず、告示前に支払われた報酬が実質的に選挙運動期間中の活動への対価を含むと判断されれば、やはり買収罪の可能性があります。
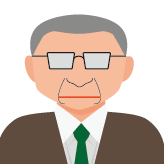
ここにインターネット選挙運動等に関する各党協議会がつくった「改正公職選挙法(インターネット選挙運動解禁)ガイドラインQ&A」を掲載します
1 買収罪
【問31】 業者(業者の社員)に、選挙運動用ウェブサイトや選挙運動用電子メールに掲載する文案を主体的に企画作成させる場合、報酬を支払うことは買収となるか。
【答】
1 一般論としては、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行っており、当該業者は選挙運動の主体であると解されることから、当該業者への報酬の支払は買収となるおそれが高いものと考えられる。
2 なお、選挙運動に関していわゆるコンサルタント業者から助言を受ける場合も、一般論としては、当該業者が選挙運動に関する助言の内容を主体的・裁量的に企画作成している場合には、当該業者は選挙運動の主体であると解されることから、当該業者への報酬の支払は買収となるおそれが高いものと考えられる。
【問32】 業者に、選挙運動用ウェブサイトや選挙運動用電子メールに掲載する文案を主体的に企画作成させ、その内容を候補者が確認した上で、ウェブサイトへの掲載や電子メール送信をさせる場合、報酬を支払うことは買収となるか。
【答】
一般論としては、候補者が確認した上でウェブサイトへの掲載や電子メール送信が行われているものの、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行っており、当該業者は選挙運動の主体であると解されることから、当該業者への報酬の支払は買収となるおそれが高いものと考えられる。
【問33】 業者に、候補者に対する誹謗中傷を機械的に監視させる場合、報酬を支払うことは買収となるか。
【答】
業者が、主体的・裁量的でなく、機械的に誹謗中傷を監視する行為を行っている場合、当該行為の限りにおいては直ちに選挙運動に当たるとはいえないことから、一般的には、当該業者への当該行為についての対価の支払は買収とはならないものと考えられる。
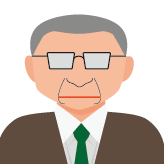
以上から、ガイドラインに沿うと事案3例は「買収となるおそれが高い」と判断できるようにも見られます。
ま と め
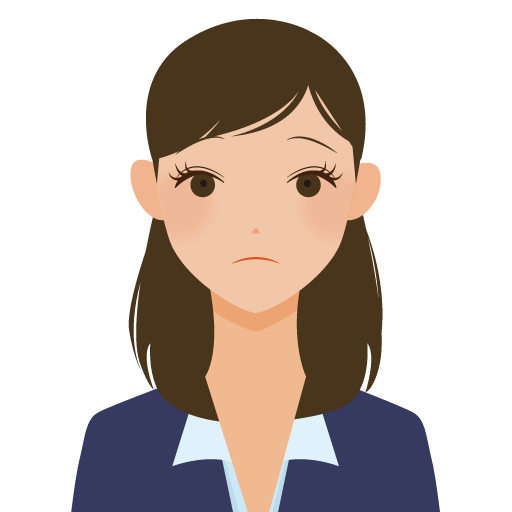
調べてみると、選挙運動期間中に「選挙事務員」として、事務所等で作業してもらい規定内の報酬を支払う以外に報酬を支払えば「運動員買収」とみられる可能性が高いようね。
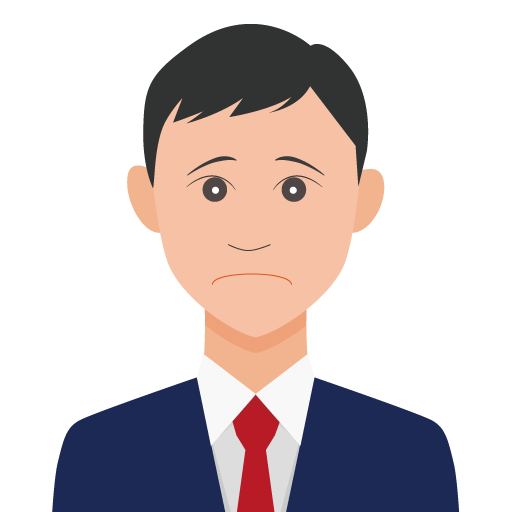
仮に業者が無報酬で、動画の撮影から編集、アップまで引き受けてくれたとしても、作業してもらった社員等に給料が支払われれば、結果、制作した企業から候補者に対する寄付行為と見なされる可能性もある。
「オウンドメディア選挙運動」で対価等が発生する場合は慎重に双方で検討する必要があるね。
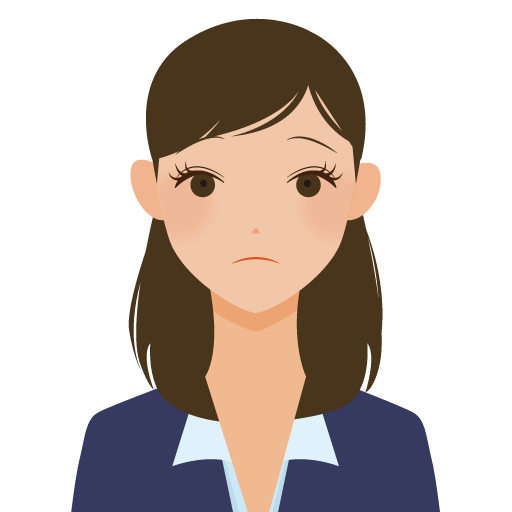
いろいろ問題が山積みされそうね。
選挙があるたび新しいケースが出てきそう。
オウンドメディア選挙運動は現代の選挙運動に不可欠な要素となったが、その運用、特に専門業者への業務委託と対価支払いは、現行の公職選挙法、とりわけ「選挙運動ボランティアの原則」と「買収罪」の規定との間で深刻な緊張関係を生んでいます。
前記の兵庫県、徳島県、東京都の事例は、この問題の複雑さと、現行法の下での法的リスクの高さを具体的に示しています。
オウンドメディア選挙運動の効果的な活用と選挙の公正性の担保という二つの要請を両立させるためには、ネット時代の選挙運動の実態を踏まえた公職選挙法の見直し、特に、外部委託可能な業務範囲や対価支払いに関するルールの明確化が不可欠です。
専門業者への委託が選挙結果を左右する現状を放置すれば、選挙が「カネで買われる」状況を招きかねません。
公正で健全な民主主義プロセスを維持するためにも、オウンドメディア選挙運動に対応した、実効性のある法整備に向けた議論を深めることが喫緊の課題でとなるでしょう。
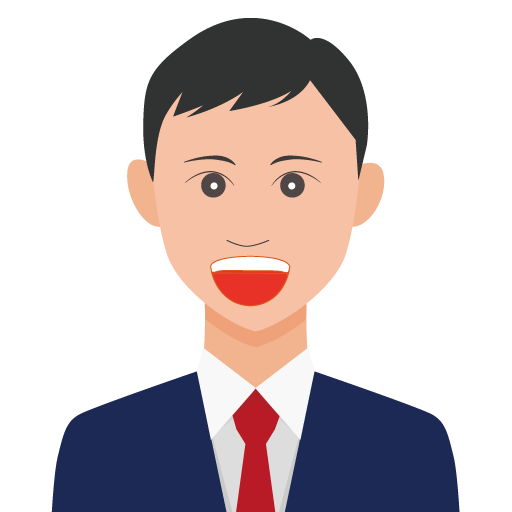
様々な方面から問題提起されているけれど、一番良くないのは「技術の要するオウンドメディア選挙運動に対価が生じることをを見過ごす」ことだと思う。
是非とも、早急に必要な法整備をして直近の選挙から対応してほしいと思う。